| 宮坂木造研究開発室の木造の家づくりガイド | |||||||
 |
|||||||
|
住み心地の良い木造の家に 樹齢より永く暮らせるように
昔から続けられてきた造り方に現代の技術をとりいれ 変化し続けるライフスタイルの器となる木造住宅をつくりましょう |
|||||||
メンテナンス・改修・再生 人が造る物、すべてに共通したことですが、新築した木造住宅も完成したその日から老朽化が始まります。 木造住宅の快適さや住み心地の良さを保つには、まず、建物自体のメンテナンス(点検・清掃など)が必要です。 メンテナンスを繰り返すうちに、建物の仕上げの一部をやり替えたり、設備機器を交換する改修の時期が来ます。住んでいる人の家族構成が変われば、部屋の間仕切りや電気配線の変更も起きます。 年月が経ち、大規模な改修が必要になり、住む人が変わって建物の使い方も変わる場合には、再生工事によって、建物の寿命を延ばすことができます。 このように、新築後のメンテナンスや改修、再生の手が加えられることで、木造住宅は誰にとっても住み心地よく、長く使われることになります。 一軒一軒の家が、長く住み続けられることで、落ち着いた街並みの景観が整い、やがては、町の風景として多くの人の記憶に残るようになります。 |
||||||||
経年変化の異なる建築部位 [築後10年未満] 枯葉の雨樋の詰まりや雨天時の風向きなどが原因で起きる外壁の汚れ、そして室内仕上げの汚れ、 家具配置の変更による間取りの不具合が起きやすい時期です。 メンテナンスと、電気のコンセントやスイッチと家具配置の入念な検討を行なっておけば、この変化を事前 に防げます。 [築後10年] [築後20数年〜30数年以上] −建物の経年変化への対処の仕方− |
||||||||
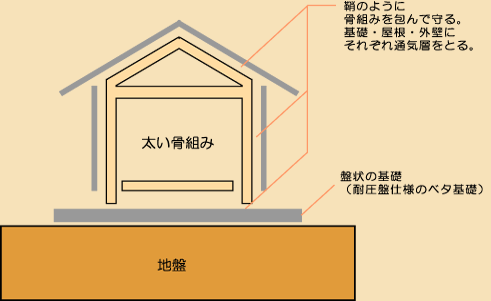 |
||||||||
| 「土壁と木の家」の外壁と屋根の通気構法、「暮らし方の自由な家」の通気構法参照 ・外装材、骨組み、内装、設備機器・配線配管の改修をしやすくする。 (「オープンビルディングという方法」参照) |
||||||||