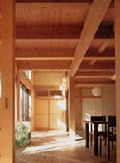| 宮坂木造研究開発室の木造の家づくりガイド | |||||||
 |
|||||||
|
住み心地の良い木造住宅に 樹齢より永く暮らせるように
昔から続けられてきた造り方に現代の技術をとりいれ 変化し続けるライフスタイルの器となる木造住宅をつくりましょう |
|||||||
軸組構法 |
||||||||||||||||||||||||||
| 日本の気候・風土になじんできたのは、軸組構法による住まい方です。 次の4つの設計事例は、その典型です。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
ティンバ−フレ−ム 日本は、現在、木材消費量の約80%を輸入している世界最大の木材輸入国です。国産材も輸入材も森林を形づくる同じ樹です。 国産材より多く使われている北米材(カナダ・米国産)をより長く使う方法の一つとして、私たちはティンバ-フレ-ムの設計に取り組んできました。 ティンバ-フレ-ムとは もともとヨ-ロッパで生まれた(14〜15世紀にドイツ、16〜17世紀に英国) 軸組構法のことです。ツ-バイフォ-が普及し始める1830年代以前の米国でログハウスと同様に200年以上建てられていました。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| いまでもニュ−イングランド地域(メイン州、ニュ−ハンプシャ−州、バ−モント州、マサチュ-セッツ州、ロ−ド アイランド州、コネチカット州)を中心に残っています。 1970年代半ばから北米で復活し、現在北米全体で年間4000棟ぐらい建てられています。 ティンバ-フレ-マ−(Timber Framer)と呼ぶ大工を養成するワークショップもさかんです。 ワークショップではティンバ−フレ−ムの実物をたてます。 |
||||||||||||||||||||||||||
| −現代のティンバ−フレ−ムの事例− | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
上の写真をクリックすると、大きな写真がみられます。
|
||||||||||||||||||||||||||
| 誰にとっても永く住める (Open-Built® Timberframe)の考え方 |
||||||||||||||||||||||||||
| 住宅を下の図のように耐用年数の異なる層(レイヤー)の集まりと考え、各層を分離できるような構法とするTedd Bensonの考え方です。 つまり、敷地は土地として在り続けるのに対し、構造体は100年から300年の耐用年数です。 屋根や外壁の外装部分は40年から100年で、取り換えが必要です。 生活する人によって間取りは10年から30年で変わっていくので、電気・水道・ガスの配線や配管は1年から10年で変わります。 家具などの配置は数ヶ月ごとに変わっているとおもいます。 このように、長い間に起きる住宅そのものと、住宅の中に起きる様々な変化に対応できなければ、誰にとっても永く住める木造住宅にはなりません。 この考え方は、ティンバーフレームだけでなく、あらゆる住宅や建物に利用できます。 この考え方の事例については、Bensonwood Homes のホームページをご覧下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||
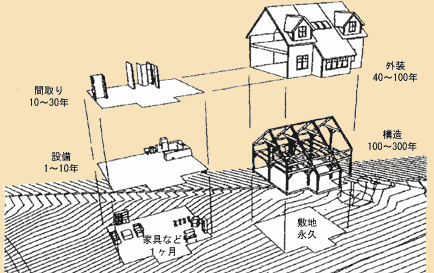 |
||||||||||||||||||||||||||
|
by Tedd Benson
|
||||||||||||||||||||||||||
| 出典: | ||||||||||||||||||||||||||
| 「ティンバ−フレ−ムの建築方法: 過去、それとも未来?どちらへ架ける橋となるか?」 −テッド ベンソン− 木造建築研究フォラム 木造軸組構法国際研究集会英語版講演録 「持続可能な木造建築の可能性を探る」 1997.4.19 より "Timber Frame Building: A bridge to the past or the future?” -Tedd Benson- "Towards the Realization of the Sustainable Wood Architecture” Wood Architecture Forum in 1997.4.19 |
||||||||||||||||||||||||||